父として、夫として、一人の人間として、がんになって本当にやりたいと思えることに出会えた

西口 洋平さん(37歳)東京都
発症 35歳/胆管がん
取材日(2017年6月28日)※年齢・地域は取材当時のものです。
「がん」という言葉を口に出した瞬間、嗚咽がこみ上げ頭が真っ白に

病気がわかったのは、2015年2月のことです。医師から「悪性腫瘍の疑いがあります」と告げられたときは、思わず「悪性腫瘍って何ですか」と、聞き返しました。それほど耳慣れない言葉だったのです。「平たく言うと、がんです」と言われて理解しましたが、その場ではまだ、先生が拍子抜けするほど冷静でした。
医師の説明が終わって病院から母に電話で「がんだと言われた」と伝えようとしたところで、全く言葉が出てこなくなったんです。何とか声を絞り出して病名を伝えた瞬間、涙も出るし、声も出なくなってしまって。電話を切り、すぐトイレに駆け込んでヒクヒクとしゃくりあげるほど泣きました。妻と娘が一人いるのですが、そのときは頭が真っ白で生活のことまで考える余裕はなかったです。
告知の翌日、妻と一緒に改めて医師の説明を受けました。そのとき、妻が治療の期間や治療費について医師に質問したのが印象に残っています。最初は「本人を目の前にして、そんなこと聞くのか」と思ったのですが、妻としては、不安や疑問を残したまま治療を始めるのはよくないと考えたんでしょうね。冷静に質問できる妻を「すごいな」と思いましたし、自分ではできなかった質問を妻がしてくれたおかげで疑問点がクリアになりました。
厳しい状態である事実を何度も突き付けられ、やりたいことをやろうと決意

告知のあと、すぐにがんの切除手術を受けましたが、開腹したものの、腹膜とリンパ節への転移があり手のつけようがなく、何もせずにお腹を閉じました。手術すれば治る可能性もあると希望を持っていたので、病名の告知よりもショックが大きかったです。
その後、3月から抗がん剤治療を始めて、4月に退院したあとは週1回通院して抗がん剤の投与を続けています。手術から約1年経った頃、状態は安定していて元気に普通の生活を送れていたので、改めてセカンドオピニオンに、どうしても手術ができないのかどうかを聞きに行きました。しかし、医師からは「こんなシビアな状態の中で手術なんかできません」というショックな返事が返ってきたんです。この状態だと本来であれば生きていることさえ難しい、こんなに元気で、積極的な治療をしようとすることはすごいと思うけれど、抗がん剤以外の治療法はない、ということを告げられました。その病院を出た時に、いつ亡くなってもいいと思えるように、やりたいことをやろうと決意したんです。
営業成績とは違う、自分にしかできない役割を果たしていく
僕の場合は手術できなかったので結果的に体の回復が早く、告知から3ヵ月後の2015年5月には仕事を再開できました。通院日は休み、週4日勤務で朝9時から夜6時までで残業はなしという勤務体制です。僕は営業だったので、成績・結果を求められる立場です。会社は、単純に数字だけを上げてほしいのであれば、僕を解雇して別の人を雇えばいい。なのに、フルタイムでは働けない、がんという病気を抱えた状況でも働かせてくれるということは、会社は僕に、何か違う役割を自分に求めているんだろうとポジティブに捉えたんです。そこで、今までの経験を後輩に伝えることはもちろん、短時間の勤務で物事を進めるために僕が行っていることなど、組織やチームにフィードバックできるのではと考えるようになりました。具体的な評価や結果につながるかどうかはわからないけれど、会社の期待や自分の役割に対しての感覚が全く変わったんです。だから、会社に対して営業成績を出せず、自分自身の収入も減りましたが、そこに不満やつらさを抱くことはなかったですね。
本人と家族では悩みの質が違うから、わかり合えない部分もある

妻とは退院した日にいろいろ話をしました。妻は専業主婦なので「仕事しないとね」とか、「まだ若いから再婚もありだよね」など、話し合うというよりも僕が一方的に話すのを妻は黙って聞いていました。妻からすれば、今後の生活について相談したくても、僕が亡くなる前提で話をすると、それを受け入れることになるのではないかという葛藤があって、返事ができなかったのだと思います。ネガティブな話ほど互いになかなか話し出しにくいですが、会話がスムーズにできないからといって、決して軽く捉えたり、考えていなかったりしているわけではない。センシティブで難しい部分ですが、そこを常に理解しておかなければいけないなと感じています。
告知されたとき幼稚園に通っていた娘は、小学3年生になりました。家にあるがんについての本や週1回の通院、おなかにある手術痕から、パパが病気で、その病気ががんであることは理解しています。今は僕も元気なので深刻な話はまだしていませんが、僕がいなくなることを想像できる年齢になるか、僕の状態が悪くなったときには、娘にも「死」について伝えなければならないと思っています。ただ、家族の中に僕がいなくなることをどう伝えればいいのか、それがすごく難しい。今も答えは見つかっていません。
がんだとわかった瞬間から、新しい人生が始まった
AYA世代のがん患者さんの中には、がんとわかって「人生が終わってしまった」と感じている人もいるかもしれませんね。僕も最初はそう思いました。でも、そうではなかった。がんだとわかった瞬間から、また新しい人生が始まったのです。
僕の場合、もしがんになっていなければ何となく仕事を続けて、可もなく不可もなくという人生が続いていたと思います。自分が本当にやりたいと思えることに出会えたのは、がんになったからこそ得られたものだと感じています。僕は、あらためて時間の使い方というものを考えました。日々生活の中で当然、惰性で動く時間もあります。でも、ずっと惰性で進むのではなく、納得のいく時間を送っていく。そういう生き方が幸せなんじゃないかと思っているんです。長いだけがいい人生でもないし、短いから悪い人生かというわけでもない。心の底から良かったと満たされることがたくさんある人生が素晴らしいと思っています。
がん患者さんの未来を変えられるのは、多くのがん患者さんの声
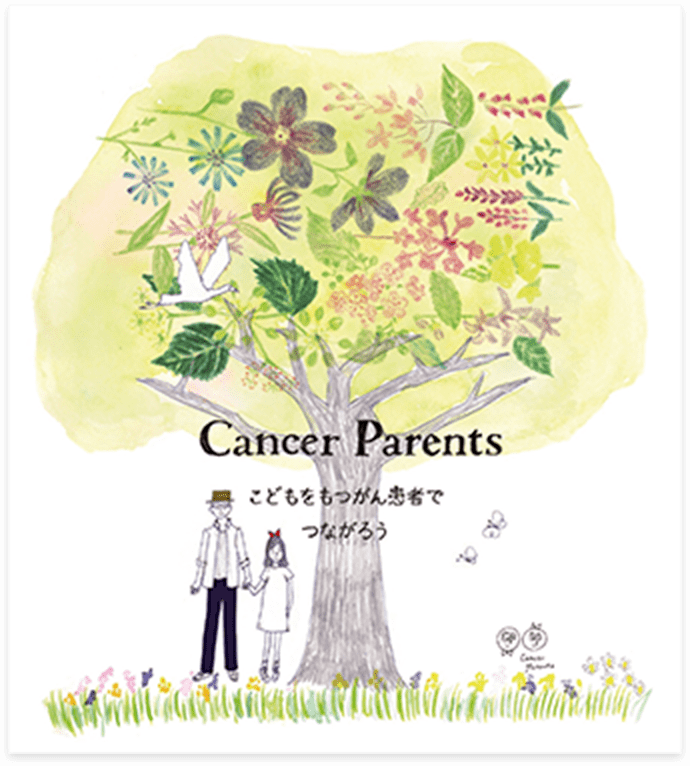
僕が「自分だからこそできることをやりたい。娘に誇れるものを形にして残したい」と模索する中で思い出したのが、同世代のがん体験者が周囲にいなくて誰にも相談できなかった、自分自身の経験です。自分と同じ悩みを抱えている人をサポートしよう。その思いから2016年4月、こどもをもつがん患者同士がつながれるコミュニティーサービス「キャンサーペアレンツ~こどもをもつがん患者でつながろう~ 」を立ち上げ、2017年6月時点で登録者数が1,000名を超えました。
仕事やお金、家族や周囲とのコミュニケーションなど、僕はたまたま場当たり的な対応で結果的に良かっただけで、失敗している患者もたくさんいると思います。家庭環境や個々の性格などに関係なく等しく受け入れる社会であればいいけれど、受け入れる側への情報が全くない。それはやっぱり患者側からの働きかけが少ないからだと思います。できない状況、行動することによるリスクがあるんです。まずはこの状況を改善し、リスクを少なくする活動をやっていかないと、これから先の発展も見えてこないと思います。
これまでも政治家や芸能人など著名ながん患者が声を上げることはありましたが、一般の患者のリアルな状態はなかなか伝わりにくいんです。一人ひとり違いがある中で、匿名でもいいので、がん患者の多種多様な意見、または総意としてうまく伝えていかないと意味がない。社会に対して知ってもらうことで患者自身の不安を減らし、家族や会社など周りの人に自分が困っていることを伝えていけるよう、インパクトのある取り組みにつなげ、拡大させていくためにも、会員数を増やし、幅広い意見を世の中に発信していきたいと考えています。
この先、もしも自分が逝ってしまって、娘が成長していく姿を見届けられなかったとしても、この活動を通して妻や娘に伝えられることがあると信じています。それに、娘が大きくなってこの活動に触れたとき、僕のことを思い出してくれたら最高ですね。
- 監修:がん研有明病院 腫瘍精神科 部長 清水 研 先生
2024年2月更新

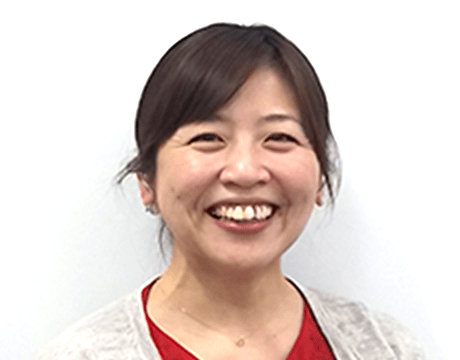 時間がかかっても夢はあきらめない心の支えになった、医師と友人の言葉
時間がかかっても夢はあきらめない心の支えになった、医師と友人の言葉
 人と違ってもいい、前向きになれなくてもいい、がんになって得たものを大切に「できること」をやっていく
人と違ってもいい、前向きになれなくてもいい、がんになって得たものを大切に「できること」をやっていく