AYA座談会
がんとともに、自分らしい働き方を探して
(座談会開催日:2025年3月7日)
岸田大島さんは、通院しながら仕事はいつも通り継続しているというお話でしたが、当初と今とでは働き方は変わりましたか。
大島業務内容は少し変わりました。もともとメインで行っていた鍼灸施術の業務が少し減り、代わりに研修の講師などの仕事が増えました。やりたかったことでもありますが、体力を考慮して意図的に変えた部分もあります。
岸田会社員であれば有給で仕事を休めることもありますが、自営業の場合、収入面での不安はありませんでしたか。

大島さんとお仕事の相棒
大島まさに、それです。自分が働かなければ収入がなくなるわけです。それが怖くて、できる限り今まで通りに働きたいとがんばっていたのかなと思います。
岸田ですよね。今、その気持ちは変わってきていますか。
大島気持ちは以前と変わりませんが、施術以外にもともと準備していた業務の比重を増やしています。これからも、治療も仕事も続ける道を模索しています。
岸田仕事を続けるために業務のバランスを変えていくということですね。今まで治療して体力面で問題はありませんでしたか。
大島罹患が判明した当初は、肺動脈の塞栓や心膜に水が溜まるなど肺がん特有の症状で、息切れが激しく大変でした。特に最初の2〜3か月は苦しい時期でした。その後、再転移が判明し入院後は、治療の副作用に加え、体力が落ちたことで回復までが大変だったと感じています。
岸田体力の回復は具体的にどうしたんですか。
大島そうですね。退院の翌日、岸田さんのがんノートのイベントに参加したのですが、そのイベントがあったおかげで、もう勢いで走り続けたという感じです。
岸田体力が下がったとか関係なく、もうがむしゃらに頑張るってことですね。
白石さんは、ヘルパーのアルバイトをしながら、どういう思いで資格の勉強を始めたんですか。
白石ヘルパーの仕事で、たまたま片麻痺(半身麻痺)の方のリハビリを手伝った時に「この人をもっと良くしたい」という気持ちが芽生えました。それをきっかけに作業療法士に興味を持ち、資格取得を決意しました。38歳から4年間、昼間はデイサービスで働きながら、夜間学校に通うという生活を続けて、作業療法士の国家試験に合格しました。始めは作業療法士として病院で働き、その後訪問リハビリの仕事に転職しました。
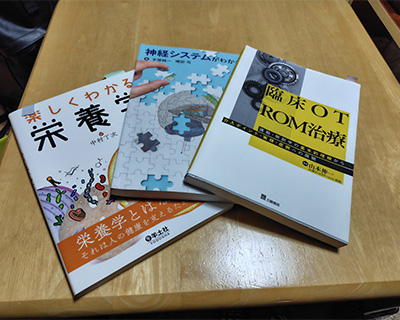
作業療法士の資格取得のためのテキスト類(白石さん)
岸田ヘルパーではなく、作業療法士になろうと思った理由はありますか。
白石福祉業界は初めてで、どんな仕事か全く予測がつかなかったものの、体に関わる仕事だし、興味があって働き始めました。実際に働いてみると面白い部分もありましたが、これまでの業界と比べ給料面が気になりもっと専門性を高めることを考えました。具体的には作業療法士の仕事が良いかな、医療職なら自分の体についてもより深く理解できて役に立つかなと感じて、選びました。
岸田作業療法士の仕事で、自分の病気の経験が役に立っていると感じますか。
白石患者さんや利用者さんの状況や心理的な背景、例えば、感じていること、考えていること、つらさなどを理解することで、より適切な対応ができるようになったと感じています。
岸田大島さんも大きくうなずいてくださってますね。
大島はい。同じようなことを感じています。
岸田白石さん、ご自身の治療面や今の状態はいかがですか。
白石甲状腺を全摘し、転移した左頚部のリンパ節も摘出しました。そのため、甲状腺の機能はなくなり、甲状腺ホルモン剤を一生飲み続けることになりました。アイソトープ治療という放射線治療を2回受け、がんの転移がなく現在は経過観察となっています。手術から12年ほどが経ち、今は半年に1回の血液検査で甲状腺の数値をチェックしています。
岸田それらによる副作用や後遺症による仕事への影響はありませんか。
白石放射線治療の影響は少ないのですが、骨に関しては影響があるかもしれません。ただし、これは潰瘍性大腸炎という別の病気の影響も関係しているようです。時間が経過するにつれて、他の慢性的な症状が徐々に出てきたり、いろいろな部分に影響が出てきたりしていますね。
岸田桑原さん、職場に復帰した時は元の職場に戻ったんですか。
桑原そうですね。休職前と同じ部署に復帰となりましたね。最初はなかなか体力がない状態でしたので、半日勤務から始めました。
岸田会社の休職制度が整えられていましたが、復職についてはどうなんですか。
桑原周囲からの復職サポートも充実していると言われています。工場内には健康管理室があり、保健師さんや複数の産業医が常駐しています。職場復帰プログラムがあり、退院後は、産業医、保健師、上司とともに現在の状況を共有していました。最初は半日から始め、産業医や主治医の意見を参考にしながら進めました。工場内では多くの社員が病気で休むことがあり、上司や人事の対応も慣れていたため、スムーズでした。体調に合わせて徐々に勤務時間を延ばし、1か月後にはフルタイムの復帰を果たしました。

休日はドライブ(桑原さん)
岸田すばらしく充実していますね。驚きました。今は、医療職のお仕事をされていますが、それはどうしてですか。
桑原病気を経験したことで、価値観が大きく変わりました。元々もの作りが好きで、高校卒業後すぐに工場に就職しましたが、病気を通じて患者さんと関わる仕事に興味を持つようになりました。社会福祉士の方と関わったことがきっかけで、復職の1年後には、働きながら通信大学で勉強し、4年後に社会福祉士の資格を取得しました。現在は病院でソーシャルワーカーとして働いています。
大島病気を経験して、価値観が変わったり、視点が変わったりしますよねー。
岸田転職してみて、今、いかがですか。
桑原仕事の量が一気に増えて、残業することもあって大変ではありますけど。患者さんから感謝されて嬉しい時もあり、やりがいは感じてますね。
岸田やりがいを感じながら仕事ができるのは素晴らしいですね。
上郡さん、1回目は3か月の入院後、スムーズに復帰できましたか。
上郡3か月間の治療を終えて退院し、約半年間自宅療養をしていました。その間に元々いた部署が解体されて、会社として私を急いで呼び戻す必要がないからか、この間、会社からは1か月に1度、軽く症状を聞かれる程度でした。体力が戻ってきたタイミングで復職しました。会社の復職トレーニングに沿って、1ヶ月間は短時間の資料作成や慣らし作業を行い、どの部署に戻るかを探しながら進めました。
岸田新しく配属された部署はいかがでしたか。
上郡復職トレーニング中、次の部署が決まるまでの間に、他の社員が休職から復帰するのをサポートしました。自分も病気の時期があり、自分の復職経験が役立てたことに対してうれしく思いました。そのまま人事に異動し、問題なく働いていましたが、上司から「こんなこともできないのか」と言われるたびに、「自分は社会にうまく復帰できていないのでは」と自己評価が低くなり、自分を責めるようになりました。これがつらく感じたことと、「人事」というやりたい分野が見つかったため、転職を決意しました。
岸田次の転職先には、2回目の罹患時に経験された休職が5か月を超えると自然退職になるという規定がありましたね。最終的にどうなったのですか。
上郡休職を続けられず、そのまま自然退職になってしまいました。
岸田自然退職になって、今のお仕事にはどのようにつながっていったんでしょうか。
上郡自宅で療養しながら、体力をつけて、求職活動を行っていました。病歴・罹患履歴もお伝えした形で面接を受けていましたが、「本当にまたフルタイムで働けるんですか」という理由で見送られることも何回かありました。その中で、内定いただいたのが今の会社です。
岸田ちなみに今は、どのようなお仕事ですか。
上郡生活支援サービスを行っている会社の人事です。

アイスクリームで休憩中(上郡さん)
岸田仕事に支障があるような後遺症は大丈夫ですか。
上郡先月ぐらいまでは抗がん剤を続けていたので、ちょっと吐き気とか立ちくらみはあったんですけど。ほぼ在宅勤務でやらせていただいているので、ありがたいことに、仕事に支障なく働けています。
岸田在宅勤務は、いいですね。上郡さんが「在宅勤務で」って言った瞬間に大西さんが大きくうなずいてくださいましたが、大西さんは逆ですもんね。大西さん、今はどういう状況ですか。
大西前の職場を会社都合で退職したんですが、次の仕事はもう決まっています。企業向けのイベント会社で、企業や学校の謎解きイベントの企画運営をしています。お芝居したり案内したり、たまに武士になったりしています。
岸田ご自分のやりたいことをお仕事にしている印象もありますが、就労にあたって大西さんが感じている問題はどのようなことですか。
大西学生時代に罹患した影響で、アルバイトはできても正社員としての就職は難しい状態です。現在も3週間に1回、必ず点滴を受けなければならず、就職に踏み込むにはまだ厳しいと感じています。短時間のシフトはできても、長時間のシフトは難しいという問題もあります。一度だけロングシフト(10時間)を試したのですが、次の日には体調不良で動けなくなってしまいました。現状では、ショートシフトで働くのが限界だと感じています。
岸田今後、どのようなことをやりたいと考えていますか。

大西 波さん
大西今後はアルバイトを楽しみつつ、自分の経験や考えを発信していきたいと考えています。また、患者会に参加したり、小児がん向けの絵本を出版しようと先生と相談したり、自分の体験を活かしてできることを積極的に取り組んでいます。元気にのんきに生きて、今できることをやっていこうという前向きな気持ちで過ごしています。
清水お話を聞いていて、会社の規定や風土がどれだけ重要で、仕事の環境に大きく影響を与えるかということを実感しました。就労規定を見れば、その会社の人格や文化がある程度見えてくるのではないかと感じました。病気を経験したことで、みなさんの仕事に対する価値観や人生観が大きく変わったように思います。実際、仕事自体を変えた方もいらっしゃり、それぞれが体験を通じて成長し、新たな道を見つけたことが非常に印象的でした。
社会福祉士から
樋口復職プログラムが整っている企業は、まだ少数派かもしれません。中小企業など、多くの職場では仕組みとして十分に整っていないのが現実ですし、自営業の方であれば、自分自身で働き方を組み立てていく必要があります。 ですが、制度の有無にかかわらず、大切なのは、「自分がどう働きたいか」「どこに配慮が必要か」を考え、整理したうえで、自分の言葉で伝えることです。それが、復職への第一歩になります。 そのときに、私がとても大切にしているのは、「できないこと」だけでなく、「できること」も考えて伝えるということです。 治療を終えて復職する場合でも、通院しながら仕事に戻る場合でも、副作用や体力の低下、合併症の影響で「以前のように働けるか不安…」と感じるのは自然なことです。だからこそ、「この時間は通院が必要です」「この作業は難しいです」といった配慮が必要な点を、正直に伝えることはとても大切ですし、職場にとっても重要な情報です。 でも、それと同じくらい、「自分には何ができるか」を整理して言葉にすることも大切です。 職場の人たちは、病気や治療のことを十分に理解しているとは限りません。「無理をさせてはいけない」「どこまで任せていいのかわからない」と、必要以上に遠慮してしまうことがあります。 だからこそ、「これならできます」「このように働きたいです」「前と同じようにできる仕事もあります」と、自分から伝えることで、お互いが安心して関わり合える関係の土台が生まれるのだと思います。 また、復職にあたっては、両立支援制度を活用することも有効です。主治医や相談窓口といった専門家の支援を受けながら、自分に合った働き方や復職のタイミングを一緒に考えていくことができます。 その際に、主治医に書いてもらう職場提出用の「治療と仕事の両立支援に関する意見書」にも、「就業の際に注意すべきこと」だけでなく、「どのような業務が可能か」「どのくらいの時間働けるか」といった“できること”を具体的に記載してもらうことがとても大切です。 こうした支援をうまく使うためにも、復職の直前ではなく、なるべく早い段階から相談を始めることが望ましいです。 復職プログラムなどの制度がない職場でも、短時間勤務、段階的な復職、業務内容の調整、在宅勤務など、個別に相談することで柔軟に対応してもらえることがあります。 復職とは、かつての自分に戻ることではなく、いまの自分に合った働き方を見つけていくことです。 「できないこと」だけに目を向けるのではなく、「できること」を一緒に考えていく。 それが、復職を前向きに進めていくうえで、何よりも大切なことだと私は感じています。
- 監修:がん研有明病院 腫瘍精神科 部長 清水 研 先生
2025年8月更新
